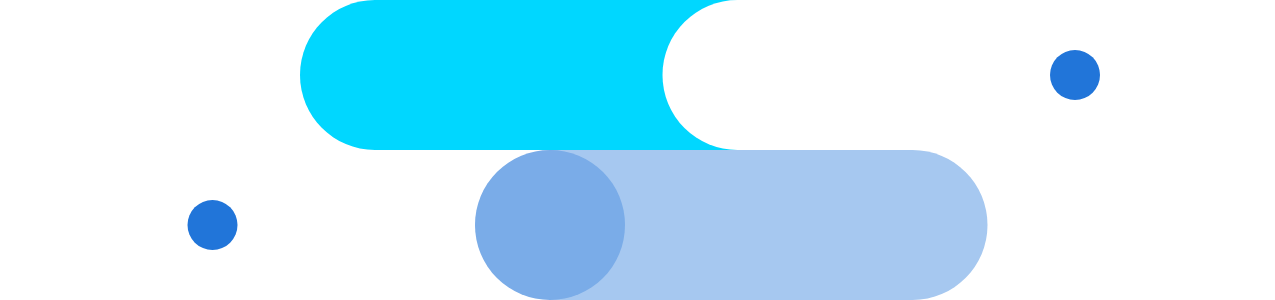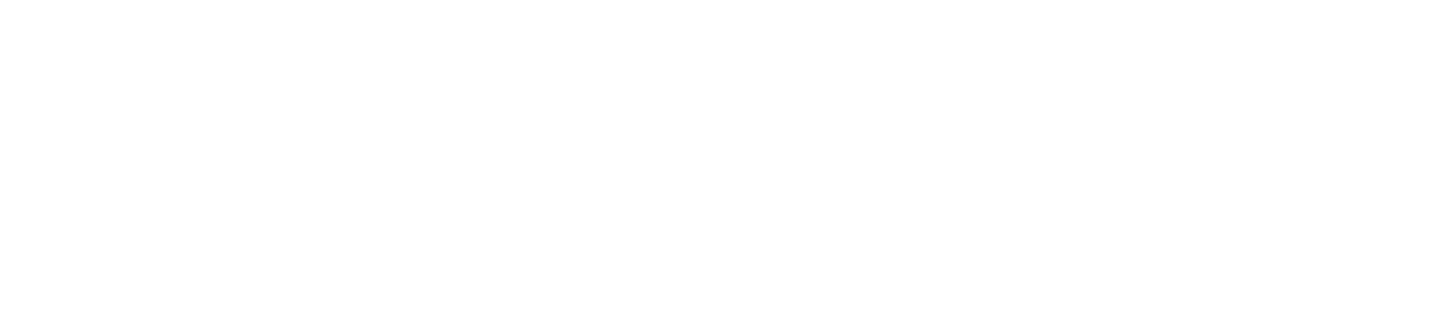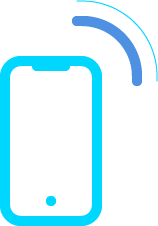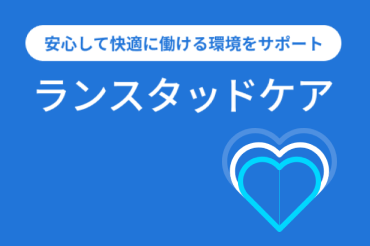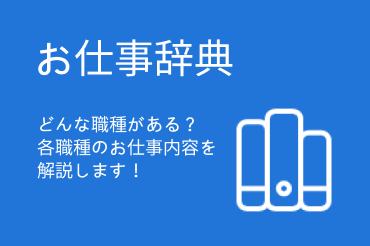ボーナスから引かれる税金や社会保険料を計算する方法とは

ボーナスにどれくらい税金や社会保険料がかかっているのかご存じですか?実際の計算式で、どれくらいの控除額が引かれているか、自分で計算してみましょう。
ボーナスにかかる税金や社会保険料の種類については、以下のページで詳しく紹介しています。
「ボーナスから引かれる税金や社会保険料とは?明細書・源泉徴収票を確認してみよう」
ボーナスにかかる税金と社会保険料の計算方法
ボーナスの手取り額は、支給額・額面から引かれる税金や社会保険料を自分で計算すれば分かります。それぞれの計算方法は次のようになります。
ボーナスから源泉徴収される所得税・復興特別所得税の計算方法
ボーナスに課税される所得税と復興特別所得税は次の計算式で求めることができます。
所得税・復興特別所得税=(ボーナス支給額-社会保険料)×税率
計算で用いる税率は、国税庁が公表している「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で確認できます。税率は0%からから45.945%まで幅広く、所得の額や扶養親族の数によって変わるので注意が必要です。なお、源泉徴収額は見込みになりますので、過不足がある場合には年末調整で修正されます。
令和6年分の税額表はこちら。ボーナスにかかる税率は15ページから記載されています。
ボーナスから引かれる健康保険料と介護保険料の計算方法
ボーナスから引かれる健康保険料は次の計算式で求めることができます。
健康保険料=ボーナス支給額(1000円未満を切り捨て)×保険料率÷2
計算のもとになるボーナス支給額は税引き前の金額で、1000円未満を切り捨てます。保険料率は加入している健康保険組合や住んでいる地域によって異なるため、事前に職場に確認しておくといいでしょう。また、40歳以上になると介護保険料が加わるため、保険料率が変化します。
なお、健康保険料(介護保険料)は勤務先が半分負担してくれます。計算した保険料が2万円なら、ボーナスから引かれる金額は1万円です。
ボーナスから引かれる雇用保険料の計算方法
ボーナスから引かれる雇用保険料は次の計算式で求めることができます。
雇用保険料=ボーナス支給額×雇用保険料率0.6%(※0.7%)
※農林水産・清酒製造業、建設業の雇用保険料率は0.7%です。
雇用保険料は保険料率が定率ですので計算しやすいでしょう。健康保険料を計算する際にはボーナス支給額の1000円未満を切り捨てていましたが、雇用保険料は切り捨てをしないので注意しましょう。
なお、計算に用いた雇用保険料率は令和6年度のもので、年度によって変わります。詳細は厚生労働省のサイトで確認してください。
ボーナスから引かれる厚生年金保険料の計算方法
ボーナスから引かれる厚生年金保険料は次の計算式で求めることができます。
厚生年金保険料=ボーナス支給額(1000円未満を切り捨て)×保険料率18.3%÷2
厚生年金保険料も雇用保険料と同様に、保険料率が定率ですので計算しやすいでしょう。計算のもとになるボーナス支給額は、健康保険料と同様に税引き前の金額で1000円未満を切り捨て、保険料も勤務先が半分負担してくれます。
ボーナスにかかる税金と社会保険料をシミュレーションしてみよう
具体的なケースをもとに、ボーナスの手取り額・額面をシミュレーションしてみましょう。
30歳 ボーナス額面40万円の手取り額をシミュレーション
東京都で働いている30歳男性のボーナスの手取り額をシミュレーションしてみます。計算の前提になる条件は以下の通りです。
- 勤務地:東京都内
年齢:30歳
職種:販売業(農林水産・清酒製造業、建設業以外の職種)
社会保険:協会けんぽ(全国健康保険協会・主に中小企業で働く従業員やその家族が加入)
扶養親族の数:0人~2人を想定して比較
所得税(復興特別所得税)は社会保険料が判明しないと計算できませんので、まずは社会保険料から計算していきましょう。
健康保険料の計算
- 健康保険料
=額面40万円(1000円未満切り捨て)×保険料率 9.98%(※)÷2
=1万9960円
※保険料率...協会けんぽの東京都の税率で、令和6年3月分(4月納付分から)が該当します。対象者が40歳未満なので、介護保険料はかかりません。保険料率は年度によって変わることがあります。
雇用保険料の計算
- 雇用保険料
=額面40万円×保険料率 0.6%
=2400円
厚生年金保険料の計算
- 厚生年金保険料
=額面40万円×保険料率 18.3%÷2
=3万6600円
続いて所得税(復興特別所得税)を計算します。まずは計算のもとになる、ボーナス支給額から社会保険料を控除した金額を求めましょう。
所得税・復興特別所得税の計算
- 所得税・復興特別所得税
=(額面40万円-健康保険料 1万9960円-雇用保険料 2400円-厚生年金保険料 3万6600円)×税率
=34万1040円×税率
税率はボーナス支給額から社会保険料の額を引いた金額と、扶養親族の数によって異なります。「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」から該当する税率を導きましょう。
源泉徴収される所得税・復興特別所得税の額
| 扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 |
| 税率 | 10.210% | 8.168% | 6.126% |
| 所得税・復興特別所得税の額 | 3万4820円 | 2万7856円 | 2万892円 |
源泉徴収される所得税・復興特別所得税の額が計算できたら、額面から税金と社会保険料を引いた手取り額が計算できます。
額面40万円のボーナスの手取り額の見込み
| 扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 |
| ボーナスの手取り額 | 30万6220円 | 31万3184円 | 32万148円 |
計算結果を見ると、扶養親族が1人増えるごとに手取り額が約7000円増えることが分かります。
手取りを増やすにはどうすればいい?転職も1つの手段
ボーナスの手取り額が思ったより少ないなと感じたら、支給額・額面を増やすための努力が必要です。ただし、長く働いているのにまわりの人より少ない、入社してから増えない...、などと感じたら、転職も選択肢の1つになります。転職先を探す際には、ボーナスが少なくても月々の基本給が多い会社や、成果がボーナスに反映しやすい会社などを中心にチェックするといいかもしれませんね。