interview論理の先に人間力をー障がいのある私が法務の道でめざすもの
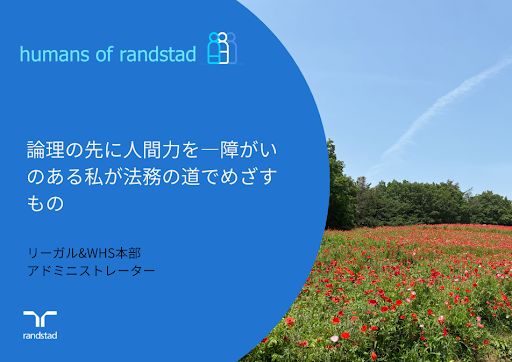
リーガル&WHS本部 アドミニストレーター
- profile
- 高校卒業後、大学時代は法学部で労働法や法制史について学ぶ。 大学在学中に障がい者手帳を取得し、障がい者採用枠での就職活動を進める。 新卒で入社した前職では人事業務を経験し、2024年にランスタッドへ入社。
「論理の美しさ」に惹かれて—法律を学んだ学生時代とプロフェッショナルへの思い

ランスタッド株式会社のリーガル&WHS本部に所属する彼女。現在は、秘密保持契約書や取引基本契約書のレビュー、外国籍スタッフの雇用に関する法務相談など、法律の知識を活かした業務に携わっています。
大学生のときに障がい者手帳を取得して以来、彼女は障がいのある人が専門職として働くことの難しさに直面してきました。今回のインタビューでは、これまでの歩みや、今の仕事に感じるやりがい、今後の展望について伺いました。
大学で法学部を選んだのは、自身の性格や関心から自然と導かれたものでした。
「私は子どもの頃から正しいことやきちんとしていることが好きで、ルールを守ることを大切にしてきました。それに、論理的な文章が好きで。高校の授業で判決文や法律の条文を読んだときに、その美しさに惹かれました。自分も論理的に話せる人になりたいと思いました」
大学時代には行政書士の資格も取得。卒業後は、障がいのあるメンバーが多く在籍する企業で人事の仕事に就きました。
「人事部で雇用率の計算や報告書の作成、助成金の申請、組織図の作成などを担当していました。職場の人間関係も良く、やりがいもありましたが、法律知識が必要とされる場面はあまり多くありませんでした」
学んだ法律を活かしたいという思いは、心の中でずっと消えることがなかったと話します。
「『法務 障がい者雇用』といったキーワードで検索しても求人の数は非常に限られており、障がいを抱えながら法律の専門職を目指すことの厳しさを痛感しました。そんなときランスタッドの法務部の求人を見つけて、何かのご縁があるかもしれないと感じ、応募を決意しました」
選考の過程では、他社との違いを強く感じたそうです。
「ほかの企業の面接では、『体調は落ち着いていますか?通勤に不安はありますか?』『配慮があれば大丈夫ですよね?』というような質問が多くて、自分に期待されている役割が不明確だと感じていました。
しかし、ランスタッドの面接では、大学時代の取り組みや資格取得の過程を丁寧に聞いてもらえて。一人の戦力として、『この人にどう活躍してもらおうか』という視点で見てもらえていると感じました。そこに強く惹かれましたね」
在宅勤務ができる点も決め手の一つでした。
「ほかの企業は出社必須のところがほとんどでした。ランスタッドはリモート勤務が基本と教えてもらい、それも含めてランスタッドに決めました」
自分を見失いそうだった—カルチャーギャップを越えて
入社して最初に感じたのは、文化の違いの大きさでした。
「前職は、保守的な雰囲気の日本企業で、新卒入社から染みついたビジネスマナーや仕事の進め方がありました。そのため、ランスタッドに入ったときは180度環境が変わって、かなり戸惑いました」
彼女は、細やかで丁寧なやり取りを大切にしてきたタイプ。以前はメールもチャットも長文が基本でしたが、現在の職場では簡潔なやり取りが主流です。
「最初は、自分のやり方を全部変えなきゃいけないのかと悩み、自分を見失いそうな感覚がありました。少しずつ会社のスタイルが理解できて、だんだん慣れてきました」
勤務形態は在宅が基本で、出社は月に1〜2回程度に限られています。
「前職では出社勤務が基本で、電車通勤やオフィスのざわざわした環境が、障がい特性上負担になっていました。いつの間にか出社することが一日の目標になってしまっていて、本来の仕事に集中できていなかったと思います」
現在は、自宅で落ち着いて仕事に向き合えるようになり、「成果を出すこと」に意識を向けられるようになったと語ります。
業務では、チャットによるやり取りに加え、直属の上司との毎週の1on1、入社時から会社生活のサポートをしてくれる「バディ」との定期連絡、人事部門による定着支援、本部内の保健師との連携など、在宅勤務でも手厚い支援体制が整っているそうです。
「何かあったときもすぐ相談できるため、孤立せずに働けています。毎日誰かしらとオンラインでつながっていて、安心して仕事に集中できる環境です」
完璧じゃなくていい—信頼が背中を押してくれた働き方の変化

入社してから、彼女の働き方や考え方には大きな変化がありました。
「以前は、自分の中で『完璧な状態』に仕上げてからでないと、人に見せてはいけないと思っていました。学生時代や前職では、それが当たり前で100%に近づけてから上司に提出していたんです」
しかし、スピード感が求められる現在の職場では、そのやり方では追いつかないと感じたそうです。
「今は、例えば契約書のコメントを作成する際、2割くらいの段階で『こんな感じで進めています』と上司に共有します。そこからアドバイスをもらって進めていきます。最初はすごく不安でしたが、『完璧じゃなくていいから、早めに教えてもらえたほうが助かる』『間違えてもいいし、何度質問してくれてもいいよ』と言ってもらえて。それが大きな転機でした」
「この案件、自分には難しいかも」と思ったときも、無理に抱え込まず、早めに相談するようになったそうです。
「以前までは、自分でなんとかしなきゃと考えていました。ある上司の方に『調整は私たちマネージャーの役割だから、遠慮なく言って』と声をかけてもらって。『ジョブ型雇用は、役割が違うだけで上下関係じゃないんだよ』という言葉に、本当に肩の力が抜けたんです」
法務部は責任が大きく、プレッシャーもかかる仕事です。それでも、心理的安全性のある環境だからこそ、完璧を求めすぎずに前向きに取り組めていると話します。
また、日々の業務では、感謝の言葉がやりがいにつながっているそうです。
「事業部の方から『ありがとうございました』とコメントをもらえることが本当に励みになります。在宅だと、自分が役に立てているのか不安になることもあると思うのですが、そういう言葉があると『このチームの一員なんだ』と実感できます」
印象に残っている案件の一つに、契約審査でのやり取りを挙げてくれました。
「あるとき、先方の法務部から要望をいただいたのですが、そのまま反映すると当社にとって不利な内容になるものでした。しかし、全面的に断るのも難しくて。そこで『ここはご要望通りに反映しますが、こちらの部分はこういう表現にしませんか?』と、中立的な言い回しを提案しました。
神経を使うし、相手あってのやり取りになるため文言にはすごく迷いました。しかし、その後『合意が取れました』と言ってもらえて。自分が考えた言葉で交渉が進んだときの達成感は、とても大きいものでした。まだまだ勉強中ですが、こうした一つひとつを積み重ねていきたいと思っています」
信頼される人になりたい—キャリアの先に見据える、人としての成長

法務のスキルやキャリアだけでなく、人としてどう在りたいか。その思いが、彼女の仕事観の軸となっています。
「私が憧れている法務の方々は、豊富な知識と実務経験をお持ちなのはもちろんのこと、人柄が本当に素敵なんです。落ち着いていて、論理的で、どんな場面でも公平・誠実に対応されていて。私もいつか皆さんのように『この人に相談したい』って思ってもらえるような、信頼される人になりたいと思っています」
目指すのは、専門性と人間力のどちらも兼ね備えた姿。その延長線上には、研究の道も見据えています。
「大学の卒業論文では、障がい者雇用の歴史や現行法の課題について考察しました。その後、前職で発表の機会が設けられ、社内外でも取り上げてもらった経験があります。現在は現場で実務を積んでいますが、将来的には働きながら大学院に通い、障がい者雇用を企業・アカデミア双方の視点からより深く研究したいという目標があります。
そのためにも、今は『素材集め』の期間だと考えています。前職のように守られた環境の会社と、今のようなスピード感のある事業会社—両方での就労経験は、自分にとって大きな財産です。実際に障がい当事者として企業に雇用された立場だからこそ、リアルな視点を持った研究ができると信じています。それが20年後、30年後であっても、いつか実現したい夢です」
そして、同じように専門職を目指す方々に、彼女はこう語りかけます。
「障がいや苦手なことを理由に、専門的なキャリアをあきらめないでほしいです。私自身も、うまくいかないことや苦しい時期がたくさんありました。今でも『この障がいがなければ』と思う瞬間はありますし、困難に直面して悩むことも度々あります。しかし、障がいがあったからこそ出会えた仕事や人がいて、だからこそ強くなれた部分もあると思っています。
ほかの人とは違う経験をしているからこそ、その人にしかできないことがきっとある。その気持ちを、ぜひ大切にしてほしいです」




